粘着・両面テープの歴史
両面・粘着テープの歴史は、古代からの進歩の歴史があります。天然アスファルトからニカワや絆創膏、ブラックテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ポリ塩化ビニルテープ、アクリル系粘着剤など多くの素材が両面・粘着テープとして利用されてきました。


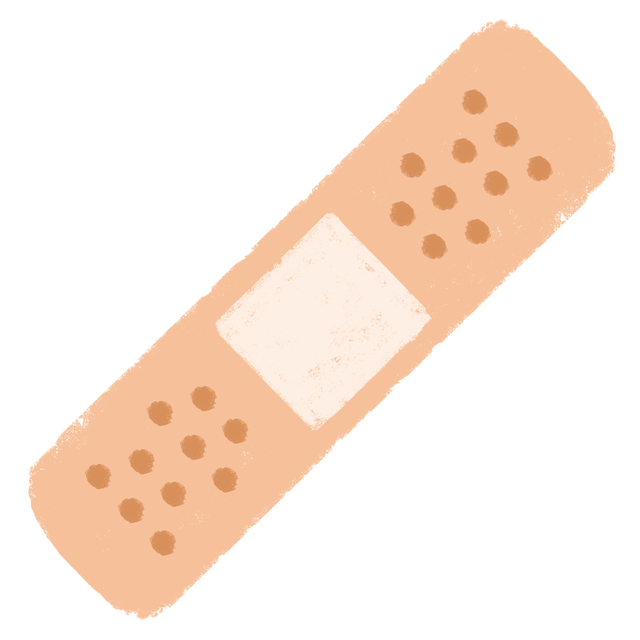

 ブラックテープ
ブラックテープ
粘着剤にとっての大きな出会いは天然ゴムあろう。
1493年~1496年に、コロンブスが2回目の航海で西インド諸島に立ち寄った時に現地でさわると弾力性があり、落としたり投げたりするとポンポンと弾むものを発見し、これが、ヨーロッパの人々とゴムとの出会いでした。
ヨーロッパの人々にとってゴムは不思議なもの、珍しいものとして注目を浴びましたが、粘着剤として、本格的に利用されるようになったのは、1870年代のアメリカで、天然ゴムをベースとした湿布薬を製造し始めました。
「温めなくても粘着力が得られ、すぐ貼れる」これは、今日の私たちから見れば当たり前のことですが、この時代になってようやく誕生した技術なのです。医療用以外には、19世紀初めから電気の利用が始まり、工業の発展は決定的となり、
絆創膏とはまったく別の分野で、電気絶縁テープが開発されました。
綿布、スフ(人造綿花)に、ゴムを両面にすり込み、さらに片面にゴム系粘着剤を塗った黒い粘着テープで、「ブラックテープ」と呼ばれました。
工業用粘着テープの元祖とも言われています。


 マスキングテープ
マスキングテープ
その後の産業革命の中でも、大きな出来事である自動車の計画生産における生産工程でマスキング用途で効率的な粘着剤の要望が強くありました。
そこで基材に含浸処理加工紙を使うことを思いついたのです。
含浸処理加工紙とは、クレープ紙という薄い紙にニカワを含浸させたものです。
クレープ紙の小さな穴を、すべてニカワでふさいでしまうのです。
これに粘着剤を塗ってテープにすると、重ねて剥がしても表裏の層割が起きません。
自動車の車体にもしっかり貼り付き、含浸処理効果によって塗料浸透もなく、剥がす際にもテープが破れません。布より薄い紙であるために、塗料の塗り分け境目の不鮮明さも解消できました。
こうして、1920年頃、初めてマスキングテープが生まれました。
そして、日本でもこうした背景の元、日本ではクレープ紙ではなく、和紙を使ってつくられていきます。
ただし、和紙は薄手ながら強度があるため、粘着剤を塗る前に含浸処理をする工程はとられませんでした。


 アクリル系粘着剤
アクリル系粘着剤
接着剤の歴史は、アスファルトやニカワ、デンプン、乳脂、豚脂、松脂、蜜ろうなど多くの素材が接着剤として開拓されてきました。
さらに、松脂と蜜ろうを組み合わせた接着剤に天然ゴムが加えられた粘着剤が誕生しました。やがて石油化学工業が台頭すると、新しいゴム系、樹脂系の素材が、粘着剤の材料として提供されます。
主材としてのゴムも天然ゴムとスチレン・ブタジエンゴムが多く用いられるようになり、ニトリルゴム系やブチルゴム系のゴムも、それぞれの特性を発揮した粘着剤として使われるようになりました。さらに「より高機能な粘着剤を生み出そう」と、人々は新しい粘着剤を自らつくりだしました。合成粘着剤の誕生です。
これにより、粘着剤技術は大きな発展を迎えます。合成粘着剤の主役は、なんといってもアクリル系ポリマー(高分子)です。アクリル系ポリマーは石油からできたプラスチックで、私たちの身近な所でも使われています。
一般によく知られているものは、アクリル板と言われている有機ガラスです。耐老化性に優れており、透明性にも優れたプラスチックで、光や紫外線をガラスよりも良く透過させるため、粘着剤の中核ポリマーとして活発に開発が進められ、今日の粘着テープの繁栄を築きました。
共同開発・業務提携
製品についてのお問合わせ・共同開発・業務提携についてはこちらへご連絡をお願いします。
-
04-2944-5151(代)
受付時間:平日8:30~17:30
- メールでのご相談・お問合わせ
